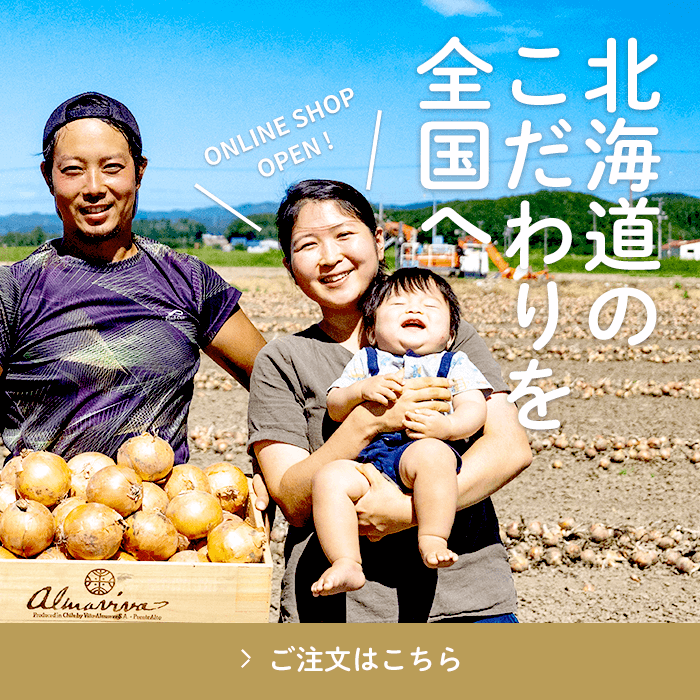「ゆめぴりか」や「ななつぼし」をはじめ、全国的においしさが認められて年々人気の高まる北海道米。最近誕生した新しい銘柄も含め、品種ごとに異なる味や粘り、それぞれに適した料理を管理栄養士の筆者が解説します。この記事を読めばあなたの好みにピッタリな北海道米が見つかるはず!白米として炊いて食べる「うるち米」だけでなく、「もち米」や「酒米」についても簡単にご紹介します。
目次
- 1 北海道米ってどんなお米?
- 2 お米の美味しさとは
- 3 独自のキャッチコピーで分かりやすく!品種紹介
- 3.1 ①もちもち甘い北海道米の極上品種『ゆめぴりか』
- 3.2 ②時間が経っても美味しさ長持ち『ななつぼし』
- 3.3 ③さっぱりとしたお米がお好みなら『おぼろづき』
- 3.4 ④やわらかくツヤと甘味が素晴らしい『ふっくりんこ』
- 3.5 ⑤農薬使用量が少なくクリーン『きたくりん』
- 3.6 ⑥一度は食べてみたい希少品種『ゆきさやか』
- 3.7 ⑦玄米がおすすめ!やわらか~い『あやひめ』
- 3.8 ⑧業務用米の有力候補『えみまる』
- 3.9 ⑨北海道米の先駆者『きらら397』
- 3.10 ⑩あっさりとした脇役ならおまかせ『ほしのゆめ』
- 3.11 ⑪業務用米の古株『大地の星』
- 3.12 ⑫丼物にピッタリ!『そらゆき』
- 3.13 ⑬必要としている人のために欠かせない『ゆきひかり』
- 4 北海道米は《もち米》もおいしい
- 5 最近、注目度が増す北海道の《酒米》
- 6 最後に
北海道米ってどんなお米?

北海道の稲作の中核地帯は石狩、上川、空知地方です。北海道の中央部から日本海にそそぐ石狩川水系に沿った地域は豊富な水資源に恵まれており、比較的暖かい気候で稲作に適しているためです。また、道南地方も暖かく気候が安定しているため、稲作が各地で行われています。
米の起源はインド、タイ、カンボジア、中国あたりという説が有力です。日本に稲作が伝わったのは紀元前3世紀ごろ。紀元1世紀には青森あたりまで広がりましたが、北海道の稲作は明治時代に入ってからなので北海道米の歴史は浅いと言えます。ただし、歴史は浅くともその後急速に発展し、安定した大量生産が可能になっているのが現代の北海道の稲作です。
北海道の稲作シーズンは本州と比べて寒冷なため、開拓当初は本州の米と同じ品種を作ることは難しいと言われてきました。そのため、北海道専用で作ることができる「美味しさ」と「寒さに対する強さ」を兼ね備えた品種の研究が盛んに行われています。
北海道米の旬は10月ごろ。本州産の米よりも植え付け時期も収穫時期も遅いため、新米が出回る旬の時期も若干遅くなります。
お米の美味しさとは

米の美味しさを判断する基準は、噛んだ時の粘りと硬さ、滑らかさなどで決まります。これらの基準は米の8割を形成するデンプン質の性質の違いと、たんぱく質の量の違いに影響されます。
デンプンの性質は「アミロース」と「アミロペクチン」の割合で決まります。
うるち米のアミロース含有量は20~30%で、一般に、アミロース含有量が高いとぱさぱさとした食感になり、低いとモチモチとした食感が楽しめます。「美味しい」と言われるコメのアミロース含有量は23%前後、またはそれよりも高めなことが多いです。ちなみにコシヒカリは20%前後、ゆめぴりかは19%未満が美味しい基準値になっています。
アミロース以外のでんぷん質はアミロペクチンです。アミロペクチンがほぼ100%のものを『もち米』と呼んでいます。
「たんぱく質含有量」も味に栄養を及ぼす重要な要素です。たんぱく質含有量が高すぎるとアミロースによる味と粘りが感じにくくなってしまうため、たんぱく質含有量は低い方が「美味しい」とされます。
独自のキャッチコピーで分かりやすく!品種紹介
筆者がそれぞれのうるち米の特徴を加味し、独断で作り出したキャッチコピーを交えてそれぞれの品種の特徴を紹介します。
①もちもち甘い北海道米の極上品種『ゆめぴりか』
2011年にデビューした品種。美味しさもさることながらCMでも多々放送され、今では北海道を代表する美味しいお米の品種です。
アミロース含有量が適度に低く、粘りがあり北海道米の中でも最上級のおいしさ。たんぱく質の低さによる炊きあがりのツヤも美しく、粒の大きさが通常の米よりも大きめな食べ応えのあるお米です。
ゆめぴりかには厳しい基準を満たしたものだけにつく「認定マーク」があります。たんぱく質含有率基準などを満たした「ブランド米の中のトップ」のゆめぴりかだけにこの認定マークが付けられます。
②時間が経っても美味しさ長持ち『ななつぼし』
「ひとめぼれ」の血を引く寒さに強い品種。ふっくらとした食感で、味、つや、粘りなどがバランスよく優れており、北海道の中心になっている品種です。
冷めても粒感がありながら硬くなりにくく、水っぽくもならずに美味しさを保てるため、お弁当や寿司にもおすすめな品種です。
③さっぱりとしたお米がお好みなら『おぼろづき』
軟らかく粘りが強い品種でやや細長い形をしています。炊くときはやや水を少なめにすると良いです。アミロース含有量は14%前後と低いです。
冷めても柔らかくて粘りがあるため、おにぎりやお弁当に多く使われます。
④やわらかくツヤと甘味が素晴らしい『ふっくりんこ』
道南で開発された「ほしのゆめ」や「きらら397」の血を引くふっくらとした食感が魅力のお米です。生育特徴の関係上、北海道の中でも比較的暖かい道南と空知地方での作付けが提唱されています。
甘味が強くツヤもあるため、おにぎりや和食に適したお米です。
⑤農薬使用量が少なくクリーン『きたくりん』
「ふっくりんこ」の血を引く、植物の病気に強い品種なため、農薬をなるべく使わずに育てることが可能です。
甘みや軟らかさ、粘りのバランスが良く、さっぱりした味。どんなおかずにも合わせやすいお米です。おにぎりや丼もの、お寿司にもどうぞ。
⑥一度は食べてみたい希少品種『ゆきさやか』
比較的新しい品種で「ゆめぴりか」より美味しいともいわれています。
粘りが強いため水加減はやや少なめにして炊かなければいけませんが、噛めば噛むほど甘味が強くなり、食べ応えがある品種です。
雪のような白い炊きあがりと美しいツヤで見た目も極上。
美味しいけれど作りづらいため、生産量が少ない品種です。
⑦玄米がおすすめ!やわらか~い『あやひめ』
粘りが強くて軟らかいお米です。甘みも適度にあるため、数品種を混ぜ合わせてバランスの良い炊きあがりを目指す「ブレンド米」にも使われます。
あやひめは玄米のまま食べると皮のプチっとした食感とコメの粘りや軟らかさの相性で食感が良く、玄米の中では食べやすい品種です。
⑧業務用米の有力候補『えみまる』
食味のバランスが良く、「ななつぼし」と同等な評価がされています。
苗を作ってから水を張った田んぼに田植えをする定植方法ではなく、種子のまま畑に直植えする「直播栽培(ちょくは、ちょくはんさいばい(じきまきさいばい))」という方法で作られる品種です。
北海道でも稲作農家が減り、1戸当たりの栽培面積が増えている中、稲作の省力化を図るために期待されている有力品種です。
⑨北海道米の先駆者『きらら397』
昔の北海道米の「美味しくない」イメージを払しょくするきっかけになった品種です。しっかりした粒感があり崩れにくく、丼もの、すし、チャーハン、ピラフ、パエリアなど幅広い用途に使えるお米です。
甘味は中程度ですが、噛めば噛むほど甘味が出るため、しっかりとした粒を噛みしめながら味わってみてください。
⑩あっさりとした脇役ならおまかせ『ほしのゆめ』
「あきたこまち」と「きらら397」の血を引き、「きらら397」の後に誕生。北海道米の美味しいイメージをさらにけん引した品種です。
甘味は少なめであっさりとした食味ですが適度な軟らかさと粘りがあり、味が濃いおかずとの相性が良いお米です。
⑪業務用米の古株『大地の星』
「ほしのゆめ」の血を引く品種でアミロース含有量が高く、粘りが少ないためチャーハンやピラフ、パエリア、リゾット、冷凍食品など加工用食品向けのほぼ業務用品種です。
「えみまる」と同じく直播栽培で作付けでき、収穫量も多いため、農家の省力化と大量生産に一役買っている品種です。
⑫丼物にピッタリ!『そらゆき』
「大地の星」の血を引く業務用米です。寒さや病気に強く、収量性も良い品種であるため、「きらら397」にとって代わる品種と言われています。
粘り気が少なく、粒感が良いのが特徴で、丼ものや弁当に適しています。
⑬必要としている人のために欠かせない『ゆきひかり』
米アレルギーの低減が期待されているお米です。正直なところ、味は「きらら397」よりも劣りますが、米タンパク質によるアレルギーのある患者用として少量が栽培されています。
米アレルギーにも個人差がありますが、「ゆきひかりじゃないと安心して食べられない!」という人のため、少量でも欠かさず作り続けられています。
北海道米は《もち米》もおいしい

前項の「お米の美味しさとは?」で触れたように、米のデンプンは「アミロース」と「アミロペクチン」の二種類があります。炊飯器で炊いて白米や玄米として食べる「うるち米」のアミロース含有量は20~30%、残りはアミロペクチンなのですが、もち米はアミロペクチンがほぼ100%です。
北海道は大面積でもち米を栽培することができるため、全国への安定生産をめざし長年品種改良が続けられてきました。そのため、美味しいもち米が収穫できるようになっています。
◆長く愛されるロングセラーもち米『はくちょうもち』
北海道のもち米ブランドのロングセラー。蒸すと真っ白で餅にしても美しいもち米です。 粘りが強く軟らかさが長持ちするため、餅にする以外にも赤飯や和菓子にもピッタリの品種。スーパーでも手に入れやすいメジャー品種です。
◆大粒のもち米『風の子もち』
「はくちょうもち」の血を引く、寒さに強く収量性が高い品種です。はくちょうもちよりも粒が大きいため、おこわや赤飯がボリューム感のある仕上がりになります。
◆ツヤがあり見た目が美しい『きたゆきもち』
「風の子もち」の血を引く平成21年にデビューした比較的新しい品種です。「はくちょうもち」と同じく、白い炊きあがりと長続きする軟らかさも兼ね備えています。しっかりした食感とツヤが良いもち米で、おこわにも向きます。
◆米菓や切り餅用の業務用『きたふくもち』
硬くなりやすいため、主に切り餅やあられなどの加工品に使われるもち米です。餅にした時の食味も良い品種です。
最近、注目度が増す北海道の《酒米》

酒米とは日本酒を醸造する原料となるお米です。正式には「酒造好適米」と呼びます。
実は、一般的に白米として食べる品種も日本酒醸造に使うことはできるのですが、日本酒は米を蒸し、麹菌を植え付けて米麹を作り醸造します。そのため、原料となる米の品質は重要。
酒米は白飯として食べる際の精米よりもより多くの米を削る必要があるため、粒が大きいものが好まれます。また、たんぱく質含有量が少ない米ほど美味しい日本酒ができると言われているため、タンパクの量は少な目。そして、麹菌の付きやすさや蒸すときの吸水率なども酒米選びのポイントです。
北海道は寒冷な土地であるため、たんぱく質含有量が高くなる傾向があります。長年、北海道で酒米を作るための研究がされてきた結果、今では美味しい日本酒を北海道米でも作れるようになりました。主に栽培されている北海道の代表的な酒造好適米の3品種を紹介します。
◆北海道米で作る日本酒の火付け役『吟風』
北海道の酒米として長く愛されている「きらら397」の血を引く酒米です。吟風で作った日本酒は味わい深く、適度な香りと旨味とコクを楽しめます。
◆すっきりとした日本酒になる『彗星』
「吟風」の血を引く品種です。たんぱく質の含有量が低く、大粒。彗星で作る日本酒はスッキリとした辛口が特徴です。
◆北海道酒米のニューフェイス『きたしずく』
きたしずくは「吟風」と「彗星」のいいとこどりをしたような、味わい深くもありながらスッキリとした飲み口の日本酒に仕上がります。味のバランスが良く、酸も感じられるさっぱりとした日本酒が味わえます。
最後に

歴史は浅いとはいえ、先人たちの熱心な研究や試験栽培によって今では美味しい北海道米が多く生産・販売されています。
今回は主に北海道米の品種やその特徴をお伝えしました。米選びの参考になれば幸いです!
同じ品種でも産地や土質・生産方法で味が違うことは多くあります。気になる品種をいくつか取り寄せ、最後は自分の舌と目で確かめてみてください。