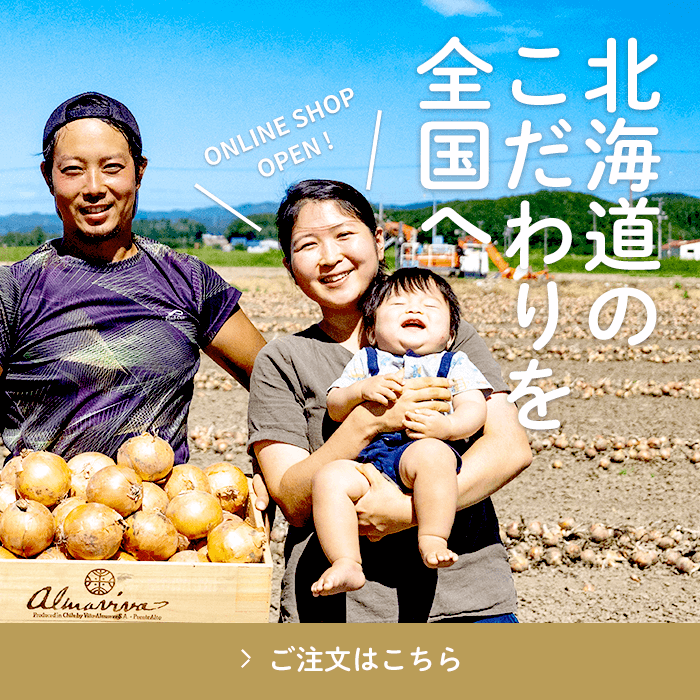ゴボウに食物繊維が多いということは有名ですが、食物繊維には大きく分けて「水溶性」と「不溶性」があります。ゴボウにはこの2種類がバランスよく含まれているため、食物繊維の働きを最大限期待することができます。他にもビタミンやミネラルなど、ゴボウに含まれる栄養素とその働きについて、管理栄養士が詳しく解説します。アクの抜き方や皮の剥き方のコツを知るだけでゴボウ料理がより美味しく、栄養満点になりますよ。
目次
「ごぼう」ってどんな野菜?

ゴボウの原産地はヨーロッパ、シベリア、中国と考えられています。中国では薬草として用いられており、食用として栽培しているのは日本だけという珍しい野菜です。
ゴボウは食べられる部分である「根」の部分しか見たことが無い人がほとんどだと思いますが、根の上に短い茎を持ち、その先に長くて大きな葉柄と葉が付きます。
ゴボウはキク科の植物であり、花も咲きます。本来、花が咲く前に収穫することから花を見ることはほとんどありませんが、アザミやキクに似た濃いピンク色の花を咲かせます。
茎や葉は暖かさを好み寒さには弱いですが、根はマイナス20℃にも耐えられる特徴を持ちます。
北海道の産地と旬

ゴボウは土を選ぶ野菜であるため、生産地域が限られます。全国一位の生産地は青森県ですが、北海道の中での一大産地は十勝管内やオホーツク管内です。他にも鵡川町や洞爺湖町でも生産されています。
北海道では4月~11月が栽培期間で、収穫は8月~11月まで。旬は秋になります。
ゴボウとは厳密には違いますが「ヤマゴボウ」とよばれる細くて漬物用のゴボウは厚沢部町で盛んに生産されています。
関東や九州ではアクの少ない「サラダゴボウ」の栽培も盛んで、サラダゴボウは春から出回ります。
ごぼうの栄養価と栄養素の働き

ゴボウは100gあたり65kcal、タンパク質1.8g、脂質0.1g、炭水化物を15.4g含みます。食物繊維を100g中に5.7gも含むため、「炭水化物―食物繊維」で求められる糖質量は9.8g。
ゴボウの特筆すべき栄養素は何といっても食物繊維です。
ミネラルは幾分含まれますが、ビタミン類はあまり多くありません。
食物繊維の種類としては「イヌリン」と呼ばれる水溶性食物繊維が多く、血糖値を上げにくいため糖尿病の人におススメの野菜と言えます。
①豊富な食物繊維
ゴボウには食物繊維が豊富に含まれています。
食物繊維には水に溶ける「水溶性食物繊維」と溶けない「不溶性食物繊維」の2種類があります。ゴボウ100g中に含まれる食物繊維5.7gのうち、2.3gは水溶性で残りの3.4gは不溶性です。
水溶性食物繊維は糖質の吸収を緩やかにし、血糖値の急上昇を防ぎます。また、食後に腹持ちも良くなるため食べ過ぎを防ぎます。他にも、腸内の不要な物質を絡め取り、体外に排出する助けもしてくれます。
不溶性食物繊維は歯ごたえがある野菜に多く、よく噛まないと飲み込めないため満腹中枢を刺激し食べ過ぎを防いでくれます。また、胃で消化されずに腸に達し、腸を刺激することで働きを活発化します。その結果、腸内に空気が入り腸内細菌も活性化するため消化も盛んになります。消化されない繊維は腸内を進む過程で他の不要な物質を便として一緒に排出する作用があり、便通の改善や大腸がんの予防にも効果があるといわれています。
②ビタミン類
ゴボウ100g中にビタミンB6 を0.1㎎、葉酸を68μg含みます。
ビタミンB6はタンパク質の代謝に関わるビタミンです。また、皮膚や粘膜の健康を保つため、不足すると皮膚炎や貧血、けいれん、むくみを起こしやすくなります。
葉酸は赤血球の形成を助けます。胎児の初期の神経管発達に重要な役割を持つ栄養素であるため、妊娠初期や妊娠を望む女性は特に不足しないように多めに摂取することがすすめられています。
③イヌリン
イヌリンは水溶性食物繊維の一種です。摂取することで体に有用な機能をもたらしてくれる食品である「機能性食品」として出回っているサプリメントもあります。
イヌリンは食後の血糖値の上昇を穏やかにするほか、便秘の改善にも役立ちます。
ご飯やパンに含まれる糖の吸収を抑制するため、血糖値が気になる方はイヌリンを多く含む食材がおすすめです。ゴボウのほか、チコリや菊芋に多く含まれています。
④ポリフェノール
ゴボウを切った時に茶色く褐変することがありますが、それがゴボウに含まれるポリフェノールです。アクとも呼び渋さや苦さがありますが、ポリフェノールは強い抗酸化作用を持ち細胞の老化を防いでくれたり、栄養素の酸化を防ぎ働きをサポートする役目もあります。
ただし、水に溶けやすい性質を持つことから、ゴボウのアク抜きをする際にある程度水に流出してしまいます。ポリフェノールの働きに期待したいのであればあえてアク抜きはせずに料理に使用すると良いですよ。色はくすんでしまいますが、渋さは油で炒めたりから揚げ・天ぷらなどの油ものに使うと感じにくくなりますし、苦みは料理の隠し味程度のものです。
⑤ミネラル
ゴボウ100g中にカルシウムを46㎎、マグネシウムを54㎎、リンを62㎎、鉄を0.7㎎、亜鉛を0.8㎎、銅を0.21㎎含みます。
カルシウムやマグネシウム・リンは丈夫な骨を、鉄は血液、亜鉛は味覚や細胞を作るために必要なミネラルです。銅はあまり栄養素として聞き慣れないかもしれませんが、鉄と同様に正常な血液を作り出すためや、健全な骨形成に必要なミネラルです。
栄養を逃がさない食べ方のコツ。皮の剥き方、アクの抜き方

ゴボウの皮付近には香りと旨味が多く含まれます。ピーラーや包丁で皮を剥くとゴボウの美味しい部分まで削り取ってしまうため、皮を剥く際は土を洗い落とし、スポンジの目の粗い部分やタワシで軽くこすり落とす程度にしましょう。アルミホイルをクシャクシャに丸めてゴボウをこすっても良いです。
ゴボウをアク抜きしすぎると旨味や風味、栄養が逃げてしまいます。切った後は酢水や水に10分程度浸すくらいでOKです。もちろん、アク抜きすることで料理の仕上がりが綺麗になりますが、アク抜きすることはゴボウの栄養素を減らすことにもなるのです。
先述した栄養素の中の「ポリフェノール」や「水溶性食物繊維」に記載がある通り、ゴボウに含まれる栄養素の中には水に溶けやすい性質を持つものが多いです。ポリフェノールや水溶性食物繊維の働きに期待したい場合はあえてアク抜きしない選択もアリ! 筆者は豚汁やすき焼きを作る際、ささがきしたゴボウをアク抜きせずに油で軽く炒めてから他の食材と合わせることでゴボウの風味を最大限に活かしています。
土付きと洗いゴボウ、選ぶならどっち?

栄養価の面で言えば、断然土付き!洗いゴボウは表面の皮を多めにむいているため、土付きのゴボウの方が栄養価が高いです。
また、土付きゴボウの方が日持ちします。土付きの場合は新聞紙に包んで冷暗所で保存すると、10度以下の場所であれば1か月ほど日持ちします。夏場は1~2週間で食べ切ったほうが無難です。
洗いごぼうは適当な長さに切り、ポリ袋などに入れて冷蔵庫の野菜室へ。こちらは1週間以内に食べ切りましょう。 乾燥するとどんどん硬くなり干からびてしまうため、乾燥を防ぐことがポイントです。
生のままと加熱、栄養価に違いは?

ゴボウは生のままと加熱では栄養価にさほど差は出ません。生よりも加熱した方がやわらかくなり食べやすく、様々な料理に使えるため、鍋物や汁物・煮物・揚げ物と様々な料理にチャレンジしてみてください。
おすすめの食べ方

ゴボウは生でも加熱しても食べられる野菜ですが、生でサラダや和え物として食べる場合はアク抜きをしたほうが色よく美味しく食べられます。
美味しさと食べやすさ、栄養を加味しても、ゴボウの栄養素を逃がさず食べられる「油を使用した料理」や「汁ごと食べられる料理」がおすすめです。たとえば、きんぴらごぼうやかき揚げ、から揚げ、豚汁、ポタージュが当てはまります。
他にも漬物や煮物、炊き込みご飯などにも利用できるため、ゴボウ料理のバリエーションは豊富です。
まとめ
ゴボウの産地や旬・栄養素からおすすめの料理法までをお伝えしました。
ゴボウを一度にたくさん食べる事は少ないかもしれませんが、汁物や煮物や炒め物、揚げ物、生食など様々な料理に利用できることが分かりましたね。
ゴボウの風味や旨味は食欲をそそります。ぜひ様々な料理に使用してゴボウ料理のレパートリーを増やしてみてください。