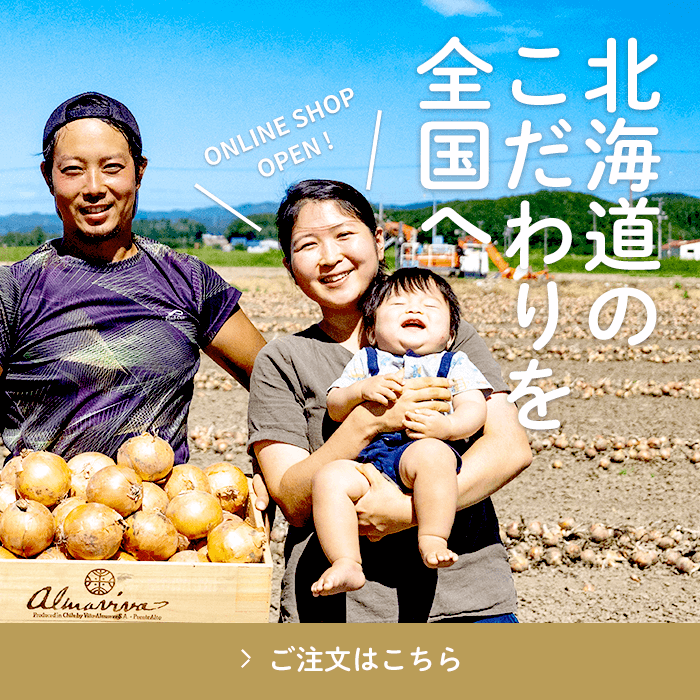北海道産のとうもろこしには様々な種類があります。品種ごとに甘さや食感に特徴があり、とうもろこし好きは品種にもこだわり購入する人もいます。
今回は甘いとうもろこしの中でも特に人気が高い「ゴールドラッシュ」について、管理栄養士が詳しく解説します。
目次
日本のスイートコーンの進化の歴史

まずはとうもろこしの歴史を紹介します。とうもろこしは本来、主食である穀物として南アメリカ大陸やアメリカ本土で栽培されていた植物です。
日本へは1500年代後半にポルトガルから渡りましたが、当時のとうもろこしは「フリントコーン」と呼ばれる家畜のエサや粉にされる甘くない種類のとうもろこしでした。
その後、明治時代に入ると北海道へアメリカから「スイートコーン系品種」という甘みの強くて皮が薄い種類のとうもろこしのタネが輸入され、全国に甘くておいしいとうもろこしが広がったとされています。 今、日本に存在する食用の品種のとうもろこしは「スイートコーン系品種」よりもさらに甘い「スーパースイート系品種」という種類に分類されるものも出回っています。
とうもろこしの品種について

とうもろこしの美味しさを決める大きな要因は「農家の土づくり」「栽培方法」「天候」もありますが、もう一つ重要なのが「タネ」です。1本のトウモロコシも元々は1粒のタネから育ちます。その種がすぐれてなければおいしいとうもろこしはできないのです。
タネ、いわゆる品種によって味が変わるので特におすすめの品種を紹介します。
ゴールドラッシュ~ロングセラーの人気品種~

北海道のスイートコーン系の中でも定番の品種です。日本の種苗メーカーである「サカタのタネ」が開発した品種で、同じ「ゴールドラッシュ」の中にも「ゴールドラッシュ86」、「ゴールドラッシュ88」、「ゴールドラッシュ90」などがあります。この数字は種をまいた後収穫まで86日前後、88日前後、90日前後かかるという日にちの目安です。ただし、数字がついているゴールドラッシュも、道の駅やネットでは「ゴールドラッシュ」としか表記されてないことがほとんどです。
ゴールドラッシュは実が大きく成長し、皮が薄く、甘くてみずみずしいことが特徴のとうもろこしです。でんぷん質はやや少なめなので、加熱しても口の中でモチっとしづらいのが特徴です。焼きとうもろこしやコーンスープにするにはゴールドラッシュがおすすめです。
味来(みらい)〜ゴールドラッシュより薄皮が薄い〜

粒の皮が薄く、果肉が柔らかい品種です。
ゴールドラッシュよりもでんぷん質が少なく、新鮮なものは生でフルーツのように食べられます。加熱するとプリっとした実からジューシーなとうもろこしジュースが出るような感覚です。
とうもろこしの実の薄皮が気になる人や、あふれる果汁を楽しみたい人におすすめの品種です。
サニーショコラ〜ジューシー爽やかな果汁〜

サニーショコラは黄色いとうもろこしでありながら生食で食べられる品種。薄皮が柔らかくフルーティーな味わいのとうもろこしの人気品種です。
もちろん茹でてから食べてもOK!果物が含むものと同じ糖類である「果糖」が多いので、加熱後は冷やした方が甘みを強く感じます。
ピュアホワイト〜シャキシャキ食感の白いとうもろこし〜

白いとうもろこしは黄色い品種よりもでんぷん質が少ないので生でも美味しく食べられることが特徴です。
ピュアホワイトは白いとうもろこしの代表格の品種。糖度が高く、よく冷やしてから生で食べると甘みをより強く感じます。茹でて粗熱を取ってから冷やして食べると、よりでんぷん質を感じずフルーツのように食べることができます。
ロイシーコーン〜白いとうもろこしの中でも人気品種〜

「白い」の語順を変えて「ロイシー」という名前なのかと思われがちですが、「しロイ!おイシー!スイートコーン」のごろ合わせが名前の由来の白いとうもろこしです。
ピュアホワイトは少々肌色を帯びた白ですが、ロイシーコーンは真っ白で見た目が美しいのが特徴です。実が大きく育ち、甘みも強く、食べ応えがある白いとうもろこしです。
北海道産のとうもろこしが甘くておいしい理由

北海道産のとうもろこしが特に美味しいといわれている理由はやはり、昼夜の温度差も関係します。
北海道の夏は日中の気温が30度前後まで上がりますが、朝晩は10度台まで冷え込みます。とうもろこしは日中に日光に当たって糖を作り、夜はその糖を使って呼吸します。夜が暑いと呼吸の速さが早くなり、糖の消費が激しくなり、夜温が低いと糖の消費を防ぐことができます。北海道は夜温が低いことから、日中とうもろこしが作った糖を夜に消費せずに貯めることができるので、甘いとうもろこしとなるのです。
とうもろこしの美味しい食べ方
鮮度が良いとうもろこしは冷やして生のままでも食べられますが、茹でたての熱々を食べるのもとうもろこしの醍醐味ですよね。家庭で簡単にできるおいしい茹で方を紹介します。
ジューシーで甘い【茹でる】

とうもろこしの皮を最後の1~2枚だけ残して実が薄皮で覆うようにむき、とうもろこしが浸る程の水と、塩(水の量の2%程度)を加えた鍋に入れて中火で加熱。沸騰後は弱火~中火で6分程茹でましょう。水から茹でることでふっくらジューシーに茹で上がります。
粒感をより楽しみたい方は沸騰したお湯に入れて4~5分茹でると良いです。
簡単で味が凝縮!【電子レンジでチン】

薄皮を残したとうもろこしをそのまま電子レンジに入れ、500~600wで5分間加熱。粗熱を取ったらとうもろこしの皮の付け根から1㎝の実の部分を皮の上から包丁で切り落とします。とうもろこしの頭の方から押し出すようにするとツルンと取り出せますよ。お好みで塩を振って召し上がれ!
家庭で作るとうもろこしレシピ
筆者は管理栄養士でありながら、とうもろこしも生産する農家の嫁でもありますが、素材の味を生かしたコーンスープは塩と牛乳だけで作るのが筆者流です。
また、北海道札幌市の有名な公園「大通公園」では、ワゴンで販売している焼きとうもろこしが超有名。北海道に観光しに来たつもりになって、焼きとうもろこしをほおばってみてはいかがでしょうか。また、子ども受け抜群なとうもろこしご飯もおすすめです。
コーンスープ(4人分)

とうもろこし(2本)を芯に沿って包丁で実を切り落とし、小鍋に入れる。とうもろこしのカサの半分くらいにまで水を入れ、蓋をして中火で5分間加熱する。ミキサーに鍋の中身をすべて入れ、牛乳(200ml)を加えてポタージュ状になるまでミキサーを回す。
鍋に移し、塩(小さじ1弱)を入れて弱火で温めれば完成。薄皮が気になる場合は粗目のザルで濾してください。性能が良いミキサーを使うと薄皮が気にならず滑らかに仕上がります。
コーンの粒も楽しみたい場合はすべてミキサーに入れず、少量よけておきましょう。鍋の中でハンドブレンダーで攪拌してもOK。冷製スープにすると、とうもろこしに含まれる果糖のおかげでより甘みを強く感じることができます。粗熱を取った後に冷蔵庫で2時間以上冷やしてみてください。
実だけ!焼きとうもろこし(2~4人分)

フライパンにバター(小さじ2)、実だけを包丁で削いだとうもろこし(2本分)をフライパンに入れ、全体の色が変わるまで炒めます。醤油(大さじ1)、砂糖(小さじ2)を入れた後、全体に絡めながら焦げ付かないように炒めれば完成。
お好みでブラックペッパーやおろしにんにくを入れたり、仕上げに溶けるチーズを入れて溶かしてもおいしいです。
とうもろこしご飯(4人分)

米(2合)をとぎ、炊飯器の釜に入れて水を2合の目盛りまで入れる。酒(大さじ2)、塩(小さじ1)、昆布(5㎝四方)も釜に入れ、とうもろこし(1本) を芯に沿って包丁で実を切り落とし、実と芯も釜に入れて通常通り炊飯する。
炊きあがったら昆布を取り出し、茶碗に盛ってからバター(お好み)を乗せて完成。醤油を垂らすと危険な美味しさに!
おつまみにもピッタリなレシピ
甘みが強いトウモロコシは辛党の人にはあまり好まれないことも。そんな時にはサクサクした食感のかき揚げにしたり、甘辛い味付けにするとお酒のおつまみとして食べることもできますよ。
バターコーンのレシピは農家さん直伝の超簡単バージョンです。
とうもろこしのかき揚げ

生のとうもろこし(1本)を芯に沿って包丁で実を切り落とし、ボウルへ入れる。てんぷら粉(大さじ4)をとうもろこしにまぶし、水(大さじ3)を入れて粉が見えなくなるまで混ぜる。
天ぷら鍋やフライパンに揚げ油を適量入れ、170℃になるまで加熱したらカレー用スプーンでタネを落とす。箸でかき揚げの厚みが出ている個所を軽く刺し、きつね色になるまで揚げる。(フライパンで少量の油で作る場合は裏返す)
ニンジンの千切りや玉ねぎのスライスを混ぜてかき揚げにしても良いです。天つゆでもおいしいですが、天然塩で素材の味を楽しんでみて!
まとめ
人気のスイートコーン「ゴールドラッシュ」の特徴を中心に、とうもろこしを使った簡単レシピをご紹介しました。美味しいとうもろこしが育つ条件は北海道の気候はもちろん、「農家の腕」や「愛情」も重要なポイントです。農家が愛情をかけて育てたとうもろこし、茹でるだけでなく様々な料理で堪能してみてくださいね。